分子栄養学でわかった「むくみ」と「薬が効かない」体の仕組み
こんにちは、腸活・食べる美容アドバイザーのnoriです🌿
今日は、関節リウマチの治療中に実際に約10年ほど前に体験した「痛み止めを飲んだだけで足が2倍に腫れた日」についてお話しします。
📍その時の体験ストーリーはこちらに

あのとき体の中で起きていたことを、今は、分子栄養学の視点でようやく理解できています。
痛み止めを飲んだら足がパンパンに
関節リウマチの痛みが強かったある日、
痛み止めを飲んだ直後に、足がみるみるうちに膨らみ始め、まるで2倍に腫れたようになりました。
当時は「薬の副作用かも」と思うしかなく、怖くて薬を控えたこともありました。
でも今振り返ると、あれは薬のせいではなく、体の受け皿の問題だったのです。
体の中で起きていた “もうひとつの反応”
痛み止めを飲んだとき、体は「薬を受け止める準備」ができていませんでした。
その原因は──
アルブミンというタンパク質の不足 にあります。
アルブミンは血液中で最も多く存在し、
- 血管の中に水分を保つ
- 薬やホルモンを運ぶ
という大切な働きをしています。
しかし、当時の私は長期間の少食・ファスティングを続けており、
アルブミンを作るための材料(アミノ酸・ビタミンB群・亜鉛など)が枯渇していました。
アルブミンが不足するとどうなる?
アルブミンが不足すると、次のようなことが起こります。
- 血管の外に水分が漏れ出し、むくみが生じる
- 薬がアルブミンと結合できず、作用が不安定になる
つまり、私の体の中では「薬が効かない」「水分が溜まる」という2つの現象が同時に起こっていたのです。
薬そのものが悪かったわけではなく、薬を受け止める“体の環境”が整っていなかった──
それが、あのむくみの正体でした。
薬の反応を決めるのは「栄養状態」
分子栄養学の学びを通してわかったのは、
薬の効き方や副作用の出方には、その人の栄養状態や肝機能が深く関わっているということ。
アルブミンは肝臓で作られるため、肝臓のエネルギー不足や栄養不足があると、
薬を分解・代謝する力も落ちてしまいます。
つまり、薬が「強すぎる」「効かない」と感じる背景には、
栄養が足りず、代謝の準備ができていない というケースも多いのです。
同じような症状で悩む方へ
関節リウマチだけでなく、慢性疾患の治療中に「薬が効かない」「副作用が出やすい」と感じる方は、
一度、血液検査で「アルブミン」「総タンパク」「AST・ALT(肝機能)」などを確認してみてください。
薬が効きにくいのではなく、
“栄養で満たされた体”がまだできていないだけかもしれません。
少しずつ食べる力・吸収する力を取り戻すことが、
回復の第一歩になります。
今日も読んでくださり、ありがとうございます。
心とカラダを整えるヒントを込めて
noriより🌿
📍 あのときの異常なむくみは、薬の影響だけではなく、
体の内側の栄養状態とも深く関係していました。
分子栄養学の視点から「むくみ」の本当の仕組みをまとめた記事はこちらです。

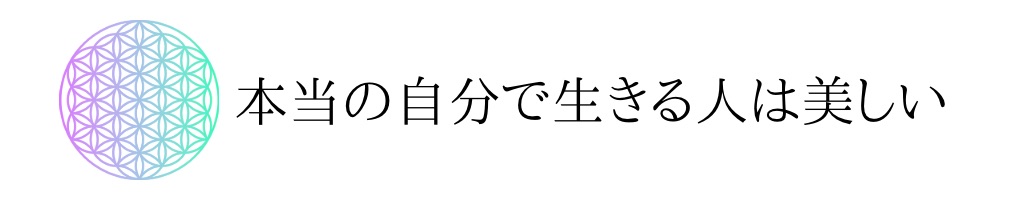






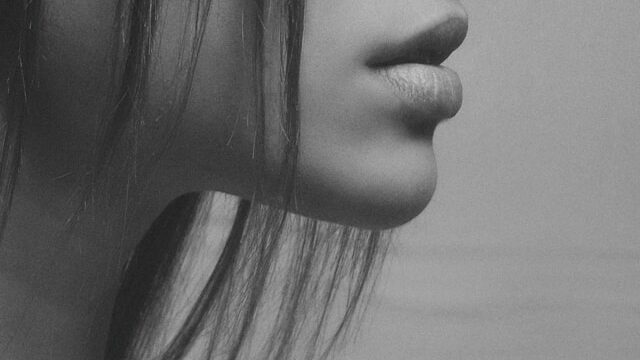



 糖化チェックで衝撃の結果!私が「血糖コントロール」を始めた理由
糖化チェックで衝撃の結果!私が「血糖コントロール」を始めた理由 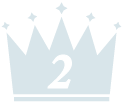 腸活でドロドロ血をリセット!体調不良とリウマチ再燃からの再出発
腸活でドロドロ血をリセット!体調不良とリウマチ再燃からの再出発  「カラダづくり(腸活)講座」はじまります!
「カラダづくり(腸活)講座」はじまります!