こんにちは、腸活・食べる美容アドバイザーのnoriです🌿
📍前回の記事では「胃酸をしっかり出すための方法」についてお話しました。

でも、食生活を整えてもなかなか消化力が回復しない…という方もいらっしゃいます。
今日はそんな方に知ってほしい「ピロリ菌と胃の関係」について、分子栄養学の視点からお伝えします。
🩺 胃酸が出ない原因のひとつに「ピロリ菌」
健康な胃では、胃酸の働きによってタンパク質が分解されます。
この“消化の第一歩”がしっかり行われてこそ、栄養は小腸で吸収され、体の細胞へ届けられるのです。
ですが、胃酸の分泌がうまくいかない場合、
その背景に「ピロリ菌(ヘリコバクター・ピロリ)」の存在が関係しているケースがあります。
🧫 ピロリ菌が胃に住みつく仕組み
胃酸は通常、pH1〜3という強い酸性です。
普通の細菌なら、この環境では生きられません。
ところがピロリ菌は、ウレアーゼという酵素を使って、胃粘膜中の尿素を分解し、アルカリ性のアンモニアを作り出します。
これが胃酸を中和し、ピロリ菌が“住みやすい環境”を作ってしまうのです。
さらに、胃の粘膜は本来6日ほどでターンオーバーしますが、
ピロリ菌はこの再生のサイクルまでも抑制してしまうことがわかっています。
その結果、傷ついた胃粘膜が修復できず、
「分泌異常」「胃酸の中和」「ターンオーバーの停止」などが起こり、
健康な消化が行えない状態になってしまうのです。
🧍♀️ ピロリ菌は特別な人だけのものではない
「胃にピロリ菌がいる」と聞くと、特別な人の話のように思っていました。
ところが、そうでもないようです。
感染経路にはいくつかの可能性があります。
- 乳児期に、親から口を介して感染
- 井戸水や衛生環境による経口感染
- 家族内感染(箸や食器の共有など)
こうした経験がなくても感染している方は少なくありません。
実際、40代以降の日本人では、およそ3人に1人が感染しているという報告もあります。
🧪 私自身の体験と学び
私自身も、分子栄養学を学ぶ中で「自分の消化力の数値」がとても低いことに気づきました。
できることから少しずつ整えてきましたが、
「もしかしてピロリ菌も関係しているのでは?」と思い、
先日人間ドックを受けた際に、オプションで血液検査を追加してみました。
結果は、また改めてお伝えしますね🌿
【11月18日New✨追記】
ピロリ菌検査の結果が出てきましたので、記事にしました。

💡 まとめ|胃の健康は“消化力の起点”
ピロリ菌は、私たちの「消化のはじまり」である胃の働きに深く関わっています。
胃酸が出にくい、食後に胃が重い、鉄不足が改善しない…といった方は、
食事だけでなく胃そのものの環境を見直すことも大切です。
分子栄養学的に見ると、吸収できる体づくりは「胃」からはじまります。
見落としがちなピロリ菌の影響も、心とカラダを整えるうえで知っておきたいポイントです。
心とカラダを整えるヒントを込めて
noriより🌿
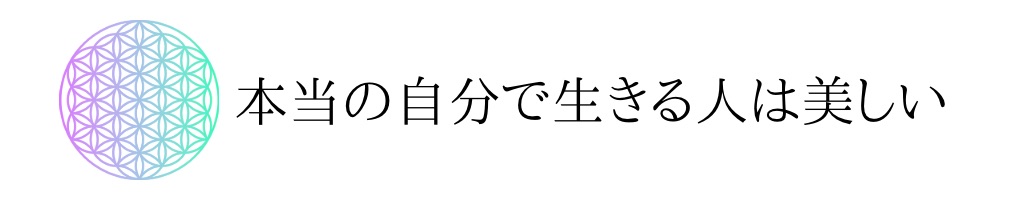
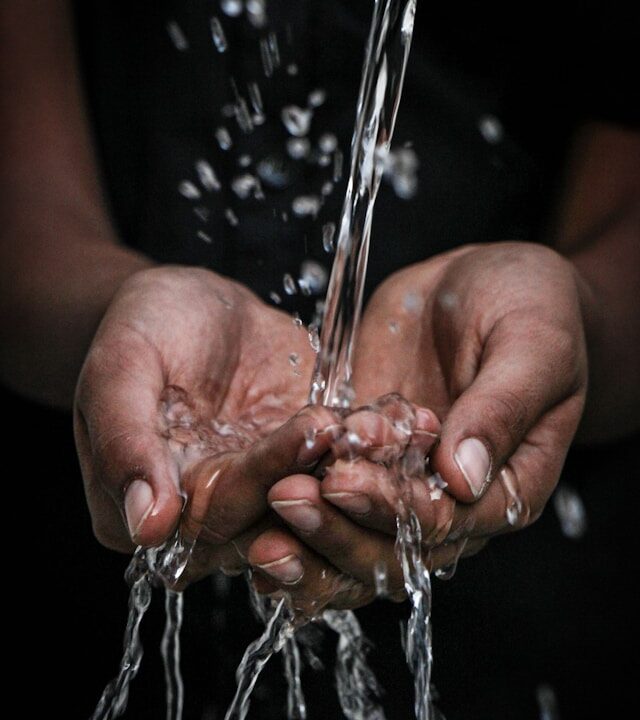






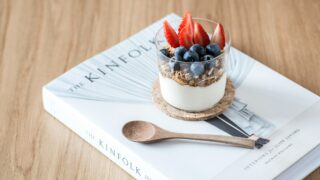


 糖化チェックで衝撃の結果!私が「血糖コントロール」を始めた理由
糖化チェックで衝撃の結果!私が「血糖コントロール」を始めた理由 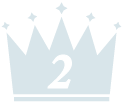 腸活でドロドロ血をリセット!体調不良とリウマチ再燃からの再出発
腸活でドロドロ血をリセット!体調不良とリウマチ再燃からの再出発  「カラダづくり(腸活)講座」はじまります!
「カラダづくり(腸活)講座」はじまります!