こんにちは、腸活・食べる美容アドバイザーのnoriです🌿
「食べること」と「食べないこと」。
一見、正反対の選択のように思えますが、実はどちらにもメリットとデメリットがあります。
🍽 食べることのメリットとデメリット
- タンパク質の合成(筋肉や組織の修復・基礎代謝の維持、ホルモンや酵素の生成)
- 脂質の生成(細胞膜・ホルモン・神経機能の材料になる)
- グリコーゲンの貯蔵(エネルギーのストック)
ただし、食事は腸内環境に負担をかけるため、腸を整え、リーキーガットなどを防ぐことが大切です。
🌙 食べないことのメリットとデメリット
- 分解が進む(体内の貯蔵エネルギーを活用)
- オートファジーの活性化(細胞の修復・若返り作用)
- タンパク質や脂肪の分解(エネルギー源として利用)
- グルコースの利用(低血糖への注意が必要)
- 腸内環境への負担軽減(腸を休ませることができる)
- 小胞体ストレスの解消(細胞の負担を減らす)
私の体験から
数十年前、アレルギーが出たときに初めてファスティングを経験しました。
そのときは体がとても楽になった一方で、筋肉量が減少。
ファスティングを何度か繰り返すうちに、代謝低下や免疫力低下で風邪をひきやすくなったり、体力がなくなったりを経験しました。安易に取り組むのはあまりおすすめしません。特に痩せ型の方は注意が必要です。
さらに、ここも大切なことですが、病気や成長期の子供は特にタンパク質の摂取は普通の方の2倍は必要です。
タンパク質は筋肉や臓器の材料になるだけでなく、メチル基の材料として「病の回復」にも深く関わっています。
メチル基はDNAの修復や解毒、神経伝達物質の合成などに必須であり、慢性的な病を持つような方は、食べないだけでは根本治癒に向かわせることは難しいのかと思っています。
もちろん、ファスティングだけで体調が良くなったという方もいます。
ただ、その場合はもともと体力があったり、症状が軽度であった可能性もあります。
一方で、慢性的な病を治癒に向かわせるためには、やはりタンパク質の摂取は欠かせません。
分子栄養学的な視点
そして分子栄養学では、このように「どちらが正しい」という一方的な答えではなく、その人の状態や体質=個体差 を重視します。
だからこそ、「食べる」「食べない」を見極めるときも、今の自分の体に合った選択をすることが大切なんです。
💡 今日のヒント
食べるか食べないかは二択ではなく、どちらも知ったうえで自分の体質や状況に合わせて選べること。
その視点を持つだけでも、日々の選択がぐっと楽になります✨
心とカラダを整えるヒントを込めて
noriより🌿
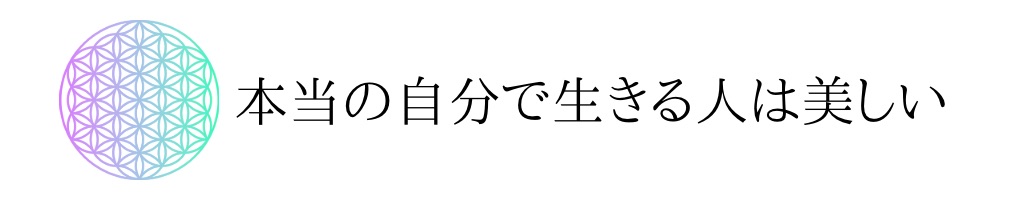




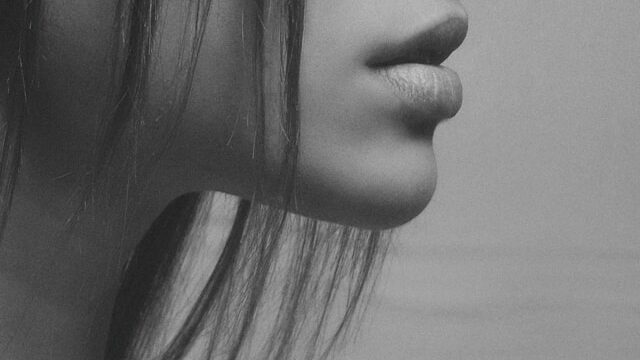






 糖化チェックで衝撃の結果!私が「血糖コントロール」を始めた理由
糖化チェックで衝撃の結果!私が「血糖コントロール」を始めた理由 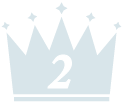 腸活でドロドロ血をリセット!体調不良とリウマチ再燃からの再出発
腸活でドロドロ血をリセット!体調不良とリウマチ再燃からの再出発  「カラダづくり(腸活)講座」はじまります!
「カラダづくり(腸活)講座」はじまります!