こんにちは、腸活・食べる美容アドバイザーのnoriです🌿
📍前回の記事では、「胆汁」が小腸を洗浄し、脂質代謝やデトックスを支える“体の石けん”のような働きをしていることをお伝えしました。

今回は、その胆汁とタッグを組んで働くもうひとつの消化液——「膵液(すいえき)」について、分子栄養学の視点から見ていきましょう。
💧 膵液とは?
膵液は、膵臓(すいぞう)から分泌される無色透明の消化液です。
1日に約1〜2リットルも分泌され、私たちが食べたものを「吸収できる形」にまで分解してくれます。
主な成分は2つ。
| 成分 | 主な役割 |
|---|---|
| 重炭酸イオン | 胃から送られてくる酸性の食塊(胃酸)を中和して、酵素が働ける中性環境を整える |
| 消化酵素群 | 炭水化物(アミラーゼ)・脂質(リパーゼ)・たんぱく質(トリプシンなど)を分解 |
*横スクロールでみてください
つまり膵液は、「消化酵素の倉庫」であり、「胃酸のバランスを保つ中和剤」でもあるのです。
🧩 胆汁と膵液の“連携プレー”
胆汁と膵液は、小腸(特に十二指腸)で同時に働きます。
- 胆汁が脂肪を乳化(細かく分散)して酵素が届きやすくする
- 膵液のリパーゼが、その乳化された脂肪を最終的に分解
この2つの連携がスムーズでなければ、脂質の吸収が不十分になり、
脂肪便・胃もたれ・脂溶性ビタミン(A・D・E・K)の吸収低下などが起こりやすくなります。
つまり、「胆汁が石けん」なら、膵液は「洗剤とブラシ」のような関係です。
どちらか一方が欠けても、汚れ(老廃物や脂質)はうまく落ちません。
🧬 分子栄養学で見る「膵液分泌のカギ」
膵液の分泌には、栄養・神経・ホルモンの3つのバランスが関係しています。
特に重要な栄養素はこちら👇
| 栄養素 | 役割 |
|---|---|
| アミノ酸(たんぱく質) | 膵臓酵素の材料そのもの。低たんぱくは分泌低下につながる |
| マグネシウム | 膵液や胆汁の流れをスムーズにする。胆道の収縮にも関与 |
| 亜鉛・銅 | 酵素の活性に必要。バランスが悪いと酵素機能が低下 |
| ビタミンC | 膵臓を酸化ストレスから守り、酵素の働きを安定化 |
| コリン | 胆汁と同様に脂質代謝を助け、肝臓〜膵臓の機能連携をサポート |
*横スクロールでみてください
また、自律神経の乱れ(ストレス・緊張)も膵液分泌を抑えてしまうため、
リラックスした食事環境がとても大切です。
🌿 膵液がうまく出ていないサイン
以下のようなサインがある方は、膵液の分泌が滞っている可能性があります。
- 食後の胃もたれ・膨満感
- 脂っこいものが苦手
- ガスが溜まりやすい
- 便がゆるい、脂っぽい
- 肌荒れ、乾燥、髪のパサつき
- だるさ、集中力の低下
これらは「酵素が足りていない」「中和ができていない」サイン。
つまり、膵臓の働きが追いついていない状態ともいえます。
☀️ 胆汁と膵液の流れを整えるためにできること
腸・肝臓・膵臓はひとつの循環システム。
その流れを滞らせないために、次の習慣を意識してみてください。
| 習慣 | 具体的なポイント |
|---|---|
| 良質な脂質をとる | オメガ3(青魚・亜麻仁油)やMCTオイルで胆汁と膵液の分泌を促す |
| たんぱく質を欠かさない | 酵素材料となるアミノ酸を安定供給 |
| 朝食時に軽くクエン酸をとる | レモン水や梅干しなどで胆汁・膵液の流れを活性化 |
| よく噛んでリラックスして食べる | 副交感神経が優位になり、膵液・胆汁の分泌が自然に高まる |
| 食物繊維を摂る | 腸肝循環を整え、古い胆汁酸を排泄するサポートに |
*横スクロールでみてください
💫 まとめ
胆汁と膵液は、「消化」だけでなく「代謝」「デトックス」「ホルモンバランス」にも深く関わる存在です。
この2つの流れが整うと、
脂肪が怖くなくなり、肌の艶・エネルギー・腸内環境まで自然と整っていきます。
食べ方と小さな習慣を見直すことで、
「消化の質」が変わり、「代謝の流れ」が生まれる——
分子栄養学的なカラダづくりの第一歩です🌿
心とカラダを整えるヒントを込めて
noriより🌿
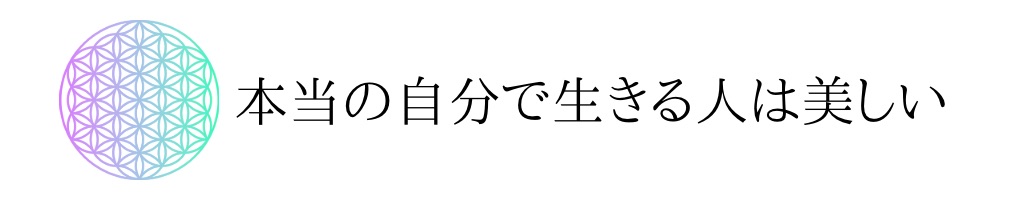











 糖化チェックで衝撃の結果!私が「血糖コントロール」を始めた理由
糖化チェックで衝撃の結果!私が「血糖コントロール」を始めた理由 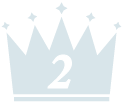 腸活でドロドロ血をリセット!体調不良とリウマチ再燃からの再出発
腸活でドロドロ血をリセット!体調不良とリウマチ再燃からの再出発  「カラダづくり(腸活)講座」はじまります!
「カラダづくり(腸活)講座」はじまります!