こんにちは、腸活・食べる美容アドバイザーのnoriです🌿
私が血糖値を意識し始めたきっかけは、AGEsテスト(糖化度測定)の結果でした。
予想以上に悪い数値を目にしたとき、測定者から「残念ながら対処方法はありません」という言葉を聞き、とても落胆したのを覚えています。
📍その記事も是非読んでみてください🌿

その後、数年は具体的な改善方法がわからず、食後の運動や糖分を控える程度しかできませんでした。
ずっとモヤモヤしたまま過ごしていたのです。
ようやく「血糖値コントロール」という考え方に出会い、自分のデータを元に栄養と生活習慣を見直すことができました。
この経験から、「血糖値」と「自律神経」が密接に関係していることを知り、とても衝撃を受けました。
🔍 私の体験:夜間低血糖と自律神経
私の場合、データを検証してみて分かったのですが、夜間低血糖になりやすい傾向があります。
低血糖になると、自律神経の交感神経(アドレナリン・ノルアドレナリン)が優位になり、夜間でも緊張状態が続きます。(本来はゆったりのリラックス状態になることが大切です。)
その結果、熟睡できず、日常にも影響が出ます。
⚠️ 低血糖が起きている時の症状
私自身や学びの中で見えてきた、低血糖に関する代表的な症状は以下の通りです。
- 頭痛
- パニック発作
- めまい
- 動悸
- ふるえ
- イライラ感(メンタルの不安定)
- 急激な疲労感
- ほてり
- 睡眠の質低下(寝汗や夜中に何度も目覚める)
- 食いしばりや歯ぎしり
これらの症状は、血糖値が不安定になることで交感神経が過剰に働き、身体や心に負担をかける結果サインです。
私自身、20代・30代の頃は頭痛で寝込むことが多く、慢性的な疲労感やほてり、歯ぎしりもありました。
更年期症状かなと婦人科にも通っていたほどです。
そして、低血糖になりやすい背景には、私自身の食習慣が大きく関係していました。
朝食を抜く、ファスティングを頻繁にする、食事を抜く、極端に糖質を減らす──。
こうした習慣は、個人の体質を無視した健康法であり、体に負担をかけることになっていたと今は強く感じます。
特にファスティングは、肝臓に十分な栄養があり機能が整っている方でないと危険になることもあります。
低血糖が起こりやすい方は、まず体づくりを整えてから取り組むことが大切です。
専門家の視点と私の想い
分子栄養学では、血糖値の変動は体全体の健康、免疫、睡眠、心の安定に深く影響すると考えます。
だからこそ、自分の体質や状況に合わせた選択が重要です。
私自身の経験からも、血糖値を安定させ、心地よい体づくりをするためには、タンパク質だけでなく、体に合ったバランスと量の食事全体が不可欠だと感じています。
特に大切なのは、血糖値の波を整える食材選びと食べるタイミング。
栄養素のバランスが整うことで、エネルギーが安定し、自律神経も穏やかに働きやすくなります。
💡 今日の気づき
血糖値と自律神経は深くつながっている。正しい食事は自律神経のバランスを整えます。
大切なのは「何を食べるか」だけでなく、「自分に合った食べ方と食事のバランス」を知ること。
それが、心とカラダを整える第一歩です。
📚関連記事🌿
血糖値について詳しくはこちらを参考に

心とカラダを整えるヒントを込めて
noriより🌿
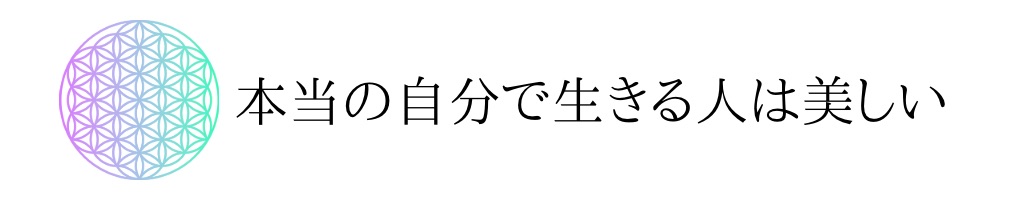



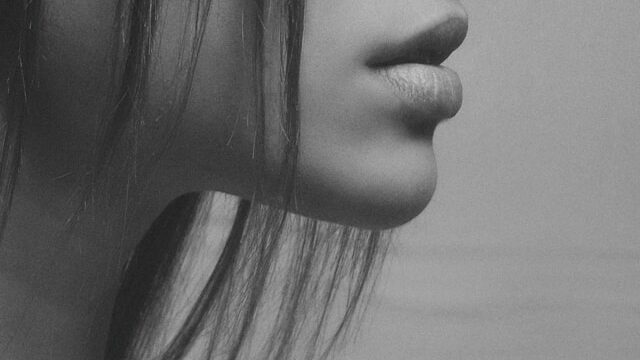


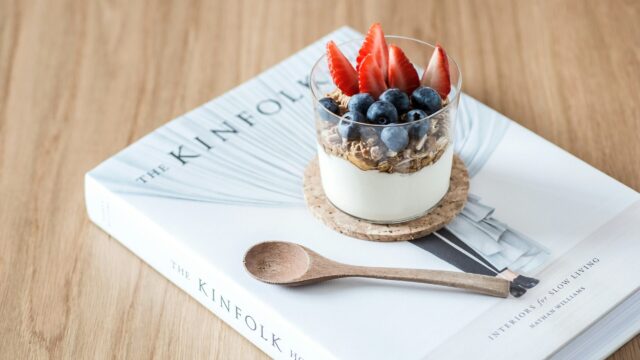




 糖化チェックで衝撃の結果!私が「血糖コントロール」を始めた理由
糖化チェックで衝撃の結果!私が「血糖コントロール」を始めた理由 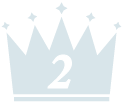 腸活でドロドロ血をリセット!体調不良とリウマチ再燃からの再出発
腸活でドロドロ血をリセット!体調不良とリウマチ再燃からの再出発  「カラダづくり(腸活)講座」はじまります!
「カラダづくり(腸活)講座」はじまります!