こんにちは、腸活・食べる美容アドバイザーのnoriです🌿
前回の記事では、「膵液」が“体のキーマン”である理由をお伝えしました。
今回はその相棒ともいえる「胆汁」との違いについて、分子栄養学の視点から掘り下げてみましょう。
🔸 胆汁と膵液、どちらも「消化液」だけど働きが違う
私たちの体では、食べたものを“分解して吸収できる形”にするために、さまざまな消化液が分泌されています。
その中でも中心的なのが、この2つ。
| 消化液 | 主な分泌臓器 | 主な役割 |
|---|---|---|
| 胆汁 | 肝臓(→胆のうで濃縮) | 脂質の乳化(分解しやすくする)/古いコレステロールの排出 |
| 膵液 | 膵臓 | 炭水化物・脂質・たんぱく質の分解/胃酸を中和して小腸環境を守る |
胆汁は「脂肪の洗剤」のような存在で、
膵液は「酵素の工場」と言えるでしょう。
🔸 それぞれの連携がうまくいかないとどうなる?
胆汁と膵液は、十二指腸で同時に分泌され、協力して消化を行います。
しかし、どちらかが不足しても、もう一方に負担がかかります。
- 胆汁不足 → 脂質が乳化されず、膵液(リパーゼ)が働きにくくなる
- 膵液不足 → 胆汁が乳化しても、最終分解できず吸収率が下がる
- 双方の滞り → 脂質代謝の低下、便秘・ガス・肌荒れ・炎症の原因にも
つまり、「胆汁と膵液」は片方では完成しないチームなんです。
🔸 分子栄養学で見る(胆汁・膵液の鍵栄養素)
| 栄養素 | 働き |
|---|---|
| アミノ酸(たんぱく質) | 消化酵素や胆汁酸合成の材料。低たんぱくは分泌低下に直結。 |
| マグネシウム | 胆管や膵管のスムーズな流れを助け、詰まりを防ぐ。 |
| ビタミンC | 酸化ストレスから肝臓・膵臓を守り、分泌細胞を安定化。 |
| コリン | 胆汁酸の生成を促し、脂質代謝と肝臓の解毒を助ける。 |
🔸 炎症コントロールとの意外な関係
実はこの「胆汁・膵液」の流れが滞ると、
腸内で二次胆汁酸や消化不全の代謝物が増え、炎症性サイトカインを刺激します。
逆に、流れがスムーズになると
- 腸肝循環が整い
- 脂肪酸バランスが改善し
- 慢性炎症が落ち着く
——という、分子栄養学的にも非常に重要なリンクが見えてきます。
つまり、「胆汁と膵液を流すこと」が、炎症体質を根本から整える第一歩なのです。
🔸 今日からできるミニセルフケア
| 習慣 | 具体的なポイント |
|---|---|
| 朝のレモン水 | クエン酸が胆汁・膵液の流れを促進。軽い酸味で消化をスタート。 |
| よく噛むこと | 副交感神経を優位にして自然な消化液分泌をサポート。 |
| オメガ3脂質の摂取 | 胆汁分泌を促し、抗炎症にも働く。青魚や亜麻仁油がおすすめ。 |
🌿まとめ
「胆汁と膵液」は、まるで舞台裏の職人たちのように、
食べたものを代謝へとつなげ、炎症を静める役割を果たしています。
体の中の“流れ”を整えることが、美しさと健康の土台。
次回はその続きとして、**「膵液が炎症コントロールに関係する理由」**を詳しくお伝えしていきます。
心とカラダを整えるヒントを込めて
noriより🌿
📍胆汁について詳しくはこちらを参考に

📍膵液について詳しくはこちらを参考に

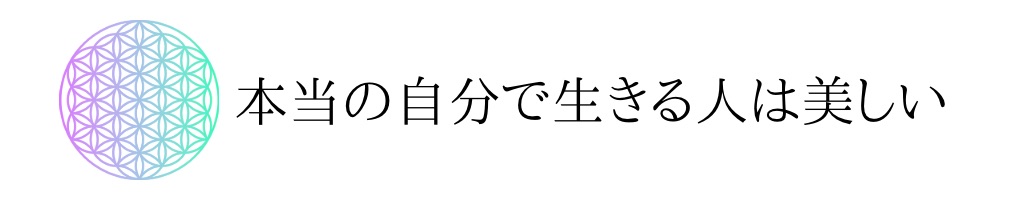










 糖化チェックで衝撃の結果!私が「血糖コントロール」を始めた理由
糖化チェックで衝撃の結果!私が「血糖コントロール」を始めた理由 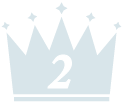 腸活でドロドロ血をリセット!体調不良とリウマチ再燃からの再出発
腸活でドロドロ血をリセット!体調不良とリウマチ再燃からの再出発  「カラダづくり(腸活)講座」はじまります!
「カラダづくり(腸活)講座」はじまります!