こんにちは、腸活・食べる美容アドバイザーのnoriです🌿
今回は「関節リウマチケア記録」第2章をお届けします。
あの診断から、私がどんな方法で体と向き合ってきたのか──
“自然療法”という選択をした当時のリアルな記録です。
📍前回の第1章|関節リウマチのはじまりーからの絶望期のお話 はこちら↓

関節リウマチと診断されたあと、私が選んだのは「薬に頼らずに治したい」という道でした。
今振り返ると、それはとても険しく、孤独で、学びの多い9年間。
漢方・食事療法・酵素栄養学など、体の声を聴きながら試行錯誤を重ねる中で見えてきたのは、「腸」と「免疫」と「心の在り方」の深いつながりでした。
この章では、私がどんな自然療法を試み、どんな壁にぶつかり、そこから何を学んだのかを、体験を通してお伝えします。
関節リウマチ診断後、私がまず考えたこと
関節リウマチの疑いがあると診断された日、処方されたのは1か月分の大量の痛み止めでした。
けれど、飲んでもまったく効かない。
痛み止めでは追いつかないほどの激痛で、薬を飲むたびに体が重くなっていく感覚がありました。
もともと薬を飲むことが苦手だっただけでなく、「薬に頼らず自分の力で治したい」という思いが日に日に強くなっていきました。
毎晩のようにパソコンで「関節リウマチ 治療法」と検索。
出てくるのは「一生薬が必要」「関節が変形していく」——そんな現実ばかり。
それでも私は、<薬以外の方法で改善する道があるのでは?>と、希望を手放せませんでした。
関節リウマチの漢方と食事療法で挑んだ9年間
再検査の結果、「関節リウマチ」と正式に診断。
その瞬間、私は<西洋医学以外の方法で治す>と心に決めました。
探し続けてたどり着いたのは、漢方クリニック。
鍼治療、漢方薬、漢方風呂など、体を温め整える療法を受けながら、養生に専念しました。
しかし、転院を重ねて3軒の漢方医にかかっても、症状は改善せず…。
むしろ季節の変わり目や疲労が重なるたびに、痛みの波が押し寄せてきました。
同時に、東城百合子さんの自然療法や甲田光雄先生の少食健康法にも取り組みました。
その流れで出会ったのが、鍼灸師の森美智代さん。
青汁一杯の少食で知られる方ですが、私は鍼治療を受けながら、断食や少食の方法も教えていただきました。
当時は「腸を休ませれば体が治る」と信じていましたが、今振り返ると、それが副腎疲労や低血糖を悪化させていたのだと気づきます。
腸と自律神経は深くつながっており、エネルギー不足の状態で断食を続けるのは、私の体には合っていませんでした。
関節リウマチ改善の糸口:酵素栄養学で見えたヒント
そんな中で出会ったのが、鶴見医師の「酵素栄養学」。
「体は食べたものでできている」——この言葉が心に響きました。
生の食材や発酵食品を取り入れ、酵素の働きを意識した食事を実践。
胃腸の調子が良くなり、肌のトーンも明るくなるなど、目に見える変化も感じられました。
それでも、関節の痛みは残ったまま。
「腸が整えば体も整う」と信じていた私は、どこかで“何かが足りない”と感じ始めていました。
関節リウマチと副腎疲労・リーキーガットへの気づき
腸と自律神経、免疫は深くつながっています。
関節リウマチを通して私が出会った副腎疲労やリーキーガットという概念は、治療の方向性を大きく変えました。
その頃、出会った書籍が安保徹先生の『免疫革命』。
免疫には自律神経のバランスが深く関係していることを知り、
「私の体は戦い続けて疲れ果てているのかもしれない」と気づきました。
また、同時期に読んだ『医者も知らないアドレナル・ファティーグ』で、副腎疲労の概念を知りました。
慢性的なストレス、睡眠不足、過剰な我慢——それらが免疫を狂わせることを学び、
少しずつ「頑張りすぎる自分を緩める」練習を始めました。
さらに、オステオパシー治療に通い始めた頃、リーキーガット(腸漏れ)という言葉にも出会いました。
体を内側から修復するには、腸の粘膜を再生させる必要がある——
その考えが、今の私の“腸活の原点”につながっています。
9年間続けた自然療法の結果と限界
関節リウマチと診断されてから9年間。
私は漢方、食事、断食、酵素栄養学、さまざまな自然療法を試し続けてきました。
ただ、結果として——
手の変形が進行し、痛みは消えないまま。
心も体も、もう限界を迎えていました。
長いトンネルの出口が見えず、
「これ以上どうすればいいのか…」と涙した日も少なくありません。
そして、2008年の診断から約10年。
私はついに、再び西洋医学の病院を訪れる決意をしたのです。
🌿まとめ
9年間の自然療法で得た学びは、「体は食べたものでつくられる」という真理でした。
関節リウマチを含む自己免疫疾患に対する食事療法や腸活、副腎疲労ケアは、私の体験の中で欠かせないテーマです。
でも同時に、心のバランスやホルモン、ストレスなど——
“栄養だけでは解けない複雑な糸”が体の中に存在することも知りました。
次章では、私が再び西洋医学に戻り、治療を受ける決意をしてからのお話しをします。
📖 当時、参考にしていた書籍たち
当時は体のことを独学で学びながら、下記の本を手に取りました。
現在は分子栄養学を学ぶ中で、当時の考え方には一部誤解もあったと感じていますが、
あの頃の経験が今の私をつくる大切な学びの土台になっています。
・『免疫革命』安保徹 著
・『医者も知らないアドレナル・ファティーグ』ジェームズ・L・ウィルソン 著
・『酵素栄養学』鶴見隆史 著
📍関節リウマチに関する体験記や学びは、すべて「関節リウマチケア」カテゴリーにまとめています。
よろしければ、ほかの記事もあわせてご覧ください🌿
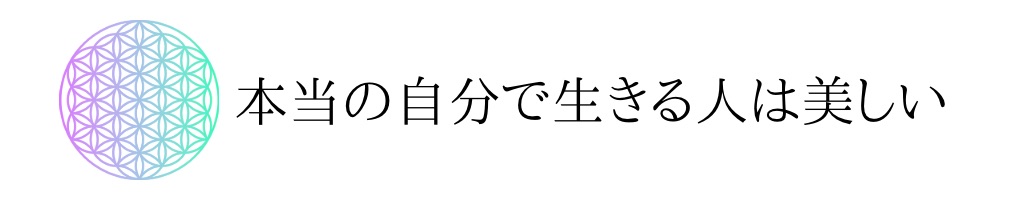



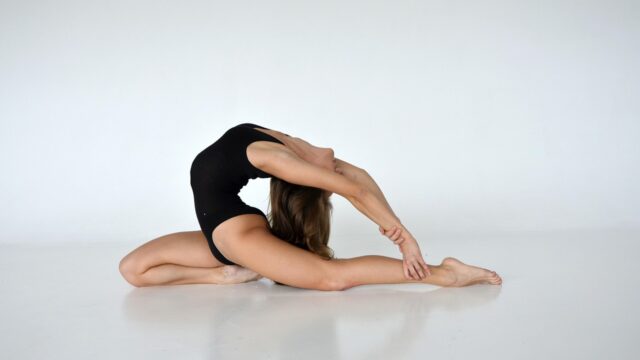






 糖化チェックで衝撃の結果!私が「血糖コントロール」を始めた理由
糖化チェックで衝撃の結果!私が「血糖コントロール」を始めた理由 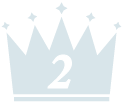 腸活でドロドロ血をリセット!体調不良とリウマチ再燃からの再出発
腸活でドロドロ血をリセット!体調不良とリウマチ再燃からの再出発  「カラダづくり(腸活)講座」はじまります!
「カラダづくり(腸活)講座」はじまります!